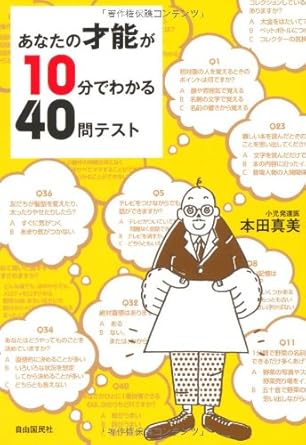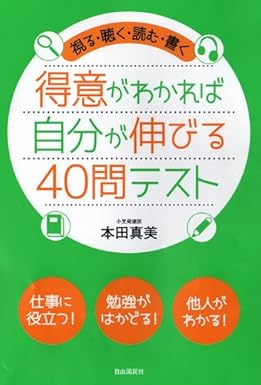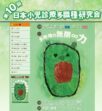医院紹介Profile
ごあいさつ
小児科医になって25年が経ちました。
これまでに外来や病棟でたくさんのお子さんたちとご家族にお会いしました。
小児科医人生の中でこどもたちから聞く一番好きな言葉を考えたときに思い浮かんだのが
「せんせい、あのね・・」でした。
「あのね、すいえいのぼうしがあかくなったんだよ」
「あのね、ほいくえんにおにがきたよ」
「あのね、おねつがでちゃった」
「あのね、おなかがいたいんだ」
「あのね、おくちにぼう(舌圧子)いれないで」
「あのね、ないてもいい?」
「あのね、がんばったよ」
どれもこれも
こどもたちのせいいっぱいの、いとおしい「あのね」
です。
あのねコドモくりにっくの最大の強みは多職種連携です。 小児科医だけでなく、看護師
助産師・栄養士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師・保育士・音楽療法士
モンテッソーリ教師などなどたくさんの専門家が在籍しています。
みくりキッズくりにっく、コドモノいっぽクリニック、やおやコドモくりにっく
医療型特定短期入所まんまる、訪問看護リハビリステーション七つの海
こどもとかぞくのサポートルームKNOT、たくさんの選択肢が私たちにはあります。
医療だけでなく、教育・福祉・行政とも連携したくさんのカタチでこどもたちと
ご家族の「あのね」にしっかりと向き合うクリニックを目指します。
医療法人社団のびた 理事長
あのねコドモくりにっく院長 本田 真美

経歴
- 東京慈恵会医科大学 卒業
- 国立小児病院
- 国立成育医療研究センター神経内科
- 都立多摩療育園 小児科
- 都立東部療育センター 小児科
- みくりキッズくりにっく 院長
資格・役職
- 医学博士
- 日本小児科学会 専門医
- 日本小児神経学会 専門医
- 子どもの心相談医
- 身体障害者福祉法第15条指定医
- コンサータ・ビバンセ処方登録医
- シダキュア・ミティキュア処方登録医
- エピペン処方登録医
- おもちゃコーディネーター
- 日本小児診療多職種学会 理事長
- 日本小児科医会 理事
- オーソモレキュラー・
ニュートリションプロフェッショナル養成講座修了
兼務
- 世田谷区教育委員会 嘱託医
- 世田谷区児童相談所 嘱託医
- 世田谷区障害児保育・医療ケア児専門委員
- 世田谷区リプロダクティブ・ヘルス/
ライツ周知啓発専門部会委員 - 世田谷区小児慢性疾病 審査委員
- 目黒区児童発達支援センター
すくすくのびのび園嘱託医 - 目黒区心身障害者センター
あいアイ館 嘱託医 - 目黒区障害児・医療ケア指導医
- 世田谷区立ふじみ保育園・
玉川保育園 園医 - 世田谷区立等々力中央保育園
医療ケア指導医 - ベネッセ桜新町保育園 園医
コンビプラザ等々力保育園 園医
ニコニコ保育園世田谷 園医 - 本田式認知特性研究所所長
所属学会
- 日本小児科学会
- 日本小児科医会
- 日本外来小児科学会
- 日本小児神経学会
- 日本小児精神神経学会
- 小児アレルギー学会
- 日本小児診療多職種学会
- 日本重症心身障害児学会
論文
- 2010年12月 Validity and reliability of a computerized cognitive assessment tool higher brain functional balancer for healthy elderly people 認知神経学vol.12 No3/4
- 2011年 Validity and reliability of Ability for Basic Movement Scale for Children(ABMS-C)in disable pediatric patients BRAIN&DEVEOPMENT 33(2011) 508-511
- 2011年 超・準超重症児を主体とした重症心身障害児(者)への痙性斜頸に対するボツリヌス毒素療法の効果 脳と発達43(2011)273-276
- 2013年 急性散在性脳脊髄炎後に低酸素性脳症を合併した高次脳機能障害児に対するリハビリテーションの経験 東京慈恵会医科大学雑誌128巻第5号163-169
- 2014年 Wechsler Intelligence Scale for Children Fourth Edition(WISC4)「絵の抹消」の有用性 The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine vol.51 No10
- 2014年 扁平足児における靴と足底装具の効果についての検討 The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine vol.51 No12
- 2014年 国立成育医療研究センターにおける発達評価外来開設 小児科第55巻第13号
- 2015年 特別なケアを必要とする児に対する病児保育のあり方(総説)病児保育研究 機関誌6号
- 2015年 Assessment of feeding and swallowing in children : Validity and reliability of the Ability for Basic and Swallowing Scale for Children(ABFS-C) BRAIN&DEVEOPMENT 37(5) 508-514
- 2017年2月 小児科診察室における子どもと親との会話からの気づき 保険の科学vol.59 No2
- 2017年3月 地域で支える障害児保育 小児内科vol.49 No3 :424-428
- 2017年7月 発達障害のリハビリテーション-多職種アプローチの実際(宮尾益知・橋本圭司著 医学書院)書評掲載
- 2021年10月 みくりキッズくりにっくのオンライン相談事業 助産雑誌vol.75 No10:752-756
- 2022年7月 『神経発達症のスクリーニング』総合リハビリテーションvol.50 no7:869-874
- 2022年7月 『開業医でもできる発達支援』小児内科 vol.54 no7:1126-1130
- 2022年10月『学校で適切に対応したい児童・生徒の困りごと55-続・学校で知っておきたい精神医学ハンドブック』(高宮静男著 星和書店)小児の精神と神経vol.62 no4書評掲載
- 2023年10月 『小児科医ができるアドボカシー活動 クリニックの小児科医による実践』 小児内科vol55 no10:
- 2023年12月 『発達障害を地域で診る プライマリ・ケアにおける対応法』月刊地域医学 Vol.37 no12:36-40
- 2024年1月 『小児科医のキャリアデザインのアドバイス』小児内科Vol.56 No1
- 2025年2月 『愛着障害-一般小児科の視点から』診断と治療社vol.53 no2:181-187
学会発表
- 2013年5月 国立成育医療研究センターにおける発達評価センターの開設経過について 第55回日本小児神経学会(大分)
- 2014年5月 ADHD/ADD児のワーキングメモリーに対するトレーニングソフトを用いた支援の有用性の検討 第56回日本小児神経学会(浜松)
- 2014年5月 小児科クリニックにおける発達専門外来の現状 第56回日本小児神経学会(浜松)
- 2014年5月 足底装具を処方した歩行障害児の年齢に伴う歩容の検討 第56回日本小児神経学会(浜松)
- 2018年5月 小児科クリニックにおける発達障害児診療の役割 第60回日本小児神経学会(東京)
- 2018年5月 定期健診にて仙骨部皮膚陥凹を認めた100症例における後方視的検討 第60回日本小児神経学会(東京)
- 2018年9月 小児科クリニックにおける重症心身障害児日中ショートステイ 第44回日本重症心身障害児学会(東京)
- 2018年9月 小児科クリニックにおけるデジタルホスピタルアートの取り組み 第44回日本重症心身障害児学会(東京)
- 2019年9月医療型特定短期入所に対する在宅重症心身障害児(者)のニーズ調査検討 第45回日本重症心身障害児学会(岡山)
- 2021年1月 『ADHD児に対するFocus Pocusの効果』 日本LD学会 第4回研究集会(富山)
- 2021年5月 『Effect of Neurocognitive Training for Children with ADHDGame based combined cognitive and neurofeedback training using FocusPocus reduces symptom severity in children with ADHD-』 第63回日本小児神経学会(福岡・オンライン)
- 2021年11月『COVID-19流効下での小児科クリニックの対応と役割』 第5回玉川医学会(東京)
- 2022年6月 『医療型特定短期入所に通所している児の利用状況の検討』 第64回日本小児神経学会(群馬)
- 2022年6月 『子どもの学習支援のための視線解析評価と上肢機能協調性評価の導入事例』 第64回日本小児神経学会(群馬)
- 2023年6月 『小児神経外によるクリニックでできる乳幼児発達支援』第65回日本小児神経学会(岡山)
- 2024年2月『こどもたちに伝えたい「自分のモノサシ」とおとななたちに伝えたい「評価のモノサシ」』 第10回日本小児診療多職種研究会 教育シンポジウム(東京)
- 2024年6月 『自閉スペクトラム症児に対する客観的指標と保護者/教師の認識の差異に関する検討』第66回日本小児神経学会(愛知)
- 2024年6月 『発達障害の各ライフステージ(幼少期・学童期・青年期・成人期)における支援および移行支援の課題について』 第61回日本リハビリテーション医学会シンポジウム(東京)
- 2025年2月『こどもの未来を考える』第11回日本小児診療多職種学会 座談会(広島)
講演会
2016年
- 『障害を持つ子どもと家族を地域で支えるために』小児在宅医療基金てぃんさぐの会
- 『障害をもつ子どもと家族を地域で支える』練馬区医師会こどもの心研究会
- 『こどもの学習と認知を考える』中央区立明石小学校PTA
2017年
- 『医療ケアが必要な子どもの保育』全国保育園保健師看護師連絡会
- 『こどもの認知特性』木更津まなび支援センター幼児言語教室
- 『発育発達がちょっと気になるお子さんとリハビリテ-ション』リハビリテーション専門職合同フォーラム世田谷
- 『できないことにはわけがある』講演 目黒区すくすくのびのび園保護者会
2018年
- 『地域クリニックで支える障害児医療』島田療育センター島田セミナー
- 『学習障害の早期発見・早期療育』第13回視覚発達支援講習
- 『自分の認知特性を知って学びに活かす』長崎県立清峰高校
- 『子どもたちの得意不得意を知る』狛江市立緑野小学校教員研修
2019年
- 『子どもたちの得意を伸ばそう』世田谷区立わかな保育園PTA
- 『医療ケアを必要とする子どもの支援』第30回全国保育園保健研究大会シンポジウム
- 『障害のあるお子さまへの医療機関と連携した地域支援』東京リハビリテーションサービス共済セミナー
- 『頭が良いって何だろう』世田谷区立砧南小学校PTA
- 『頭が良いって何だろう』世田谷区立多門小学校PTA
- 『自分の特性を知って学びに活かす』長崎県清和女子学院
2020年
- 『発達に特徴のあるお子さんの就学について』小児地域リハ研究会
- 『発達の特徴のあるお子さんの就学後について』小児地域リハ研究会
- 『認知特性に合った思考の深め方―学習スタイルの検討―』東京都市大学小規模学び合いFD
2021年
- 『コロナ禍におけるワクチン接種の課題と今後の展望』 Meiji Seikaファルマ株式会社勉強会
2022年
- 『ADHDの診断・治療について』多摩小児科懇話会
- 『こどもの発達のとらえ方 それぞれの特性を理解する』世田谷区立深沢中学校PTA
- 『小児科医が教える「小児科クリニックと上手に付き合う方法」』NPO法人かわさき市民アカデミー
- 『こどもの得意と不得意にはワケがある』(中延小学校家庭教育学級
2023年
- 『認知特性に応じた指導法』世田谷区特別支援教育研究協議会
- 『認知特性とそれに応じた指導法』八王子市立第三小学校
2024
- 『生徒と教職員の認知特性を踏まえた居心地のよい学校づくり』神奈川県立横浜旭陵高等学校
- 『認知について』日本小児科医会 子どもの心研修会
- 『ASD(自閉スペクトラム症)の子の理解と支援の実際』公益社団法人発達協会主催
2024夏のセミナー
- 『こどもの発達障害(特性)の理解と支援』世田谷区発達障害相談・療育センターげんき
- 『こどもの発達障害(特性)の理解と対応』第2回世田谷区特別支援教育研修
- 『こどものできる・できないにはわけがある』ボイタ医師研究会
2025年
- 『こどもの発達障害(特性)の理解と対応』世田谷区特別支援教室勉強会
- 『こどもの心相談医 カウンセリング実習』日本小児科医会
- 『こどもの得意不得意にはワケがある~特性に合った学び方の提案』教育開発出版株式会社 オンラインセミナー
- 『子どもの発達障害(特性)の理解と対応~その子らしさを活かすために~』東京都教育委員会
取材・マスメディア
2011年
- ひよこクラブ8月号
- ひよこクラブ11月号
- AERA with Baby 8月号
- PHP オンラインインタビュー掲載
2012年
2013年
- UNOの教科書(UNO公式本)
- Best Selection For KIDS(ギャップ・ジャパン)
2014年
- プレジデントFamily 冬号
- プレジデント Baby 2014年完全保存版
- 日経Kids+
2015年
- FIGARO maman HC-MOOK
- 1.2.3歳児の親が本当に困っていること15 小学館
- 「ゼミ勉」My Style 中2 Bennese
- 「個性にあった学習スタイル」朝日新聞7/2
- 「その勉強法 うちの子向き?」朝日新聞11/4
2016年
- 育脳Baby-mo 主婦の友生活シリーズ
- 育脳Baby-mo 中国版
- チャレ友マガジンTEAM-C Bennese
- 『ゲームが脳に与える影響』いこーよ オンライン
- 『アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所』電通報 オンライン
- ひよこクラブ7月号
- ひよこクラブ10月号
- ひよこクラブ夏秋号
2017年
- 「最新科学で解き明かす 最強の記憶術」洋泉社MOOK 分担執筆
- 「天才・奇才の作り方」 週刊ダイヤモンド1/21号
- 学びの場オンライン 発達障害と学校・医療の連携
- ひよこクラブ2月号
- ひよこクラブ6月号
- たまごクラブ9月号
- ひよこクラブ10月号
2018年
- 中3 My Style 『夏の勉強法革命』監修 Bennese
- 「科学的に正しい最強の勉強法』洋泉社MOOK 分担執筆
- PHPのびのび子育て5月号
- Kodomoe コドモエ 2月号
- ひよこくらぶ3月号
- たまごクラブ7月号
- たまひよオンライン監修
- 赤ちゃんの発達がちょっと心配なときのかかわり方【0~6ケ月】
- 赤ちゃんの発達がちょっと心配なときのかかわり方【6ケ月~1歳】
- 【乳幼児健診】1カ月健診ってどんなことをするの?
- 【乳幼児健診】3~4カ月健診ってどんなことをするの?
- 【乳幼児健診】6~7カ月健診ってどんなことをするの?
- 【乳幼児健診】9~10カ月健診ってどんなことをするの?
- 【乳幼児健診】1歳健診・1歳6ケ月健診ってどんなことをするの?
- 赤ちゃんの視力は? 聴力は? 五感はこう育つ!
- 赤ちゃんが言葉を発するまでには段階があった!
- たまひよオンライン監修
小児科医監修 1歳児の好奇心をグングン育てる知育玩具とは?
2歳の子にぴったりの知育玩具とは?
小児科医が解説 “はいはい”しない子の見守り方 促し方
【発達障がい】診断はいつから?赤ちゃんのころでもわかるの?
2019年
- 『最強のアウトプット勉強法』洋泉社MOOK 分担執筆
- 仕事旅行 オンライン掲載
- ひよこクラブ8月号
- 『脳が喜ぶ最強の勉強法』 洋泉社
- 高1・2MyVision11月号「ノート術」 ベネッセ
- 1.2才のひよこクラブ冬春号
2020年
- 「乳児健診やめないで」読売新聞5/16
- 「コロナ渦の小児科クリニック特集」読売新聞医療ルネサンス8/31~9/7シリーズ掲載
コロナと子ども<2>独自健診 新米ママ一安心
コロナと子ども<3>訪問看護 家族も心待ち
コロナと子ども<5>敏感な子 対応を柔軟に - 二子玉川経済新聞”上野毛のクリニックが乳幼児健診を無償で提供 健診自粛の自治体在住者対象に
- 『新型コロナで集団健診中止 診療所が乳幼児健診 』NHK
- 『介助必要な子 支援を…保護者感染 預け先不安』読売新聞
- 高2My Vision (Benesse)
- PHPのびのび子育て12月号
- 『学びなおしの方法』PHP business THE 21
- 『発熱は免疫が働いたサイン』AERA11月号
- 『こんなに大きくなったよ!みんなの成長写真館』1才2才のひよこクラブ2021年冬春号
- たまひよONLINE”【小児神経専門医提言】「うちの子、育てにくい」と感じたときにしたいこと”
- たまひよONLINE”いまだ再開してない地域も 「3才児健診は集団生活に入る前に絶対に受けてほしい健診」専門医
- 『コロナ渦の発達障害児支援』東京すくすく
- Growth Ring オンライン インタビュー
2021年
- 週刊ダイヤモンド 最強の中高一貫校
- ダイヤモンド・オンライン インタビュー掲載
- ベビーザらス 出産準備ブック『ベビーを育むおもちゃ』監修
- Forbes Japan 12月号
- 関塾タイムス オンライン
- 『げんき』2021年6・7月号 “うちの子”のナゾQ&A
2022年
- 中国新聞インタビュー掲載 『音で読む 要約で読む』(株)オトバンク
- ガクサン3巻 講談社モーニング
- 『大学入試シリーズ』(京都教育大学 著書掲載)
- マイナビ子育て インタビュー掲載
- no+e オーディオブック インタビュー掲載
- Benesseオンライン教育情報 インタビュー
- バリューの真実『暗記術・記憶術』NHK 7/5放送
2023年
- 代々木ゼミナール/Y-SAPIX 『医学部AtoZ』 インタビュー掲載
- 『ことばの不自由な人をよく知る本』合同出版株式会社 分担執筆
- 後期のひよこクラブ 冬号(たまひよ)
- Newsweek Japan オンラインインタビュー掲載
2024年
- スタディサプリ インタビュー掲載
- LITALICOキャリア インタビュー掲載
- LITALICO発達ナビ インタビュー掲載
- たまひよオンライン インタビュー掲載
2人の子をもつ小児科医。小学校受験を検討するも、進まない勉強にイライラ…。子どもの「認知特性」を知って自分の間違いに気づかされた【小児科医】
「何度言っても子どもに伝わらない!」その原因は伝え方がその子の「認知特性」に合ってないのかも【小児科医】 - 後期のひよこクラブ 春号(たまひよ)
- 後期のひよこクラブ 夏号(たまひよ)
- 後期のひよこクラブ 冬号(たまひよ)
- 『明日の医療を支える信頼のドクター2024年』浪速社 掲載
- Gpressせたがや(世田谷区発達障害相談・療育センターげんき)掲載
2025年
- まなびチップス インタビュー掲載
- NHK Eテレ『すくすく子育て』~ハイハイ・たっち・あんよ~出演
その他
- 子ども脳機能バランサー(協力)
- 子育てお悩み相談室 きらきら baby&Kids
- ALL ABOUT 夜泣きコーナーを連載(現在終了)
- 小児発達医まなみの診察室
- FIGARO maman vol.2
「こどもの認知特性 特集」の監修。 - プレジデントBaby 2014保存版
「0歳からの知育大百科」に掲載。 - CLINIC BAMBOO
クリニックばんぶうに掲載。 - MEDICAL QOL
メディカル クオールに掲載。 - ベビーブック付録「体・心・言葉 発達のギモンに答えます」を監修。
- ひよこクラブ、
たまごクラブの医療監修。
当院からのメッセージ
だいじょうぶ、
育ち方はいろいろ。
「この子のからだは、こころは、どんなサインを発しているんだろう?」
「どんなふうに、育ちたがっているんだろう?」
赤ちゃんや子どもの、声にならない「あのね、わたし、こう感じてるんだ」に
耳をすませて、その子らしい成長を目指す。それが「あのねコドモくりにっく」です。
今、子育てについて、たくさんの情報があふれています。
ただ、ありすぎたり、根拠にとぼしいものもあったり、つい不安になります。
そんな中で、私たちは、医学の分野で積み重ねられてきた「成長」「発育」「発達」に
関する根拠のある考えに基づいて、診療やご家族に寄りそった支援をします。
もうひとつ大事なこと。
赤ちゃんや子どもの成長って「いろいろ」です。その子らしい育ち方に
向き合うならば、医師だけじゃなく、こころのプロも、栄養のプロも、
リハビリのプロも必要。だから、私たちは、いろんな専門家がチームになって、
ひとりの子どもを支える、めずらしいクリニックになっています。
・・・ちょっと長くなってすみません。
でもいまの子どもたちを取りまく状況を考えると、時間がかかってでも、
より正確な情報を、より誠実な態度で、より安心できる関係性で、
伝えていかなきゃ、と強く感じています。
まずは、私たち自身の声(あのね)を語ってみました。
さあこんどは、私たちに声を聞かせてください。
ゆっくりでも、上手じゃなくても、だいじょうぶ。
話せないならば、泣いてくれても、怒ってくれても、だいじょうぶ。
しゃべりすぎても、だまっていても、だいじょうぶ。
子どもたちの声(あのね)を、聞かせてください。感じさせてください。
からだとこころの
「あのね」
に耳をすませる。
あのねコドモくりにっく
あのねの診療モットー①
多職種連携とたくさんの選択肢
あのねコドモくりにっくは子どもの専門家集団です。
医師、看護師、助産師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育士、幼稚園教諭、医療社会福祉士、音楽療法士、管理栄養士、児童支援員、相談支援専門員、特別支援学校教諭、運転士など17 職種 70 名以上の専門家が在籍しています。
私たちは「さまざまな分野の専門家が互いに協力し合う」多職種連携を大切にしています。
多職種のスタッフが連携することによって、お子さまやご家族さまに、薬や注射といった一般的なクリニックの医療だけでなく、お子さまの生活のすべてにたくさんの選択肢を提供させていただくことができるのです。
クリニックは目的別に3つのフロアからなり、3つの診察室のほか、個別相談室11部屋、運動療法室2部屋、集団療法室、計測室、健診専用室、看護相談室、安静室、処置室、感染予防室など設備も充実しています。
子育てのご不安やご心配に対して、多職種がかかわる私たちのクリニックにしかできない多くの側面や視点からサポートをさせていただきます。
あのねの診療モットー②
経過観察はしません
クリニックを受診したとき、健診を受けたとき、医師や看護師から
「もうすこし様子を見ましょう」と言われたことはありませんか。
私たちは、診療やサポートの際に「様子を見ましょう」「経過観察しましょう」
という言葉は使わないように心がけています。
「こんなときはどうすればいいですか?」
「こういうことが困っています。」
「うちの子、これがまだできません。」
子育て中の保護者様からよく聞かれることばです。
そんなとき私たちは、それぞれの困りごとに対する専門家が、
具体的でわかりやすいアドバイスをすることで、
ご家族がおうちでも安心して育児に向き合えるようサポートすることを心がけています。
あのねの診療モットー③
おせっかいな診療をします
私たちスタッフは全員、子どもたちが大好きで小児科クリニックで働くことを選びました。
子どもたちがつらい時は家族のように寄り添い、
子どもたちが成長したときは保護者様と一緒に喜び、
子どもたちの「できた!」「やったー!」をいちいち応援したいと思っています。
私たちは過保護でおせっかいな診療を心がけています。
かかりつけクリニックとしてお子様の成長に私たちも一緒に関わらせていただけると嬉しいです。
あのねの診療モットー④
根拠に基づいた診療をこころがけます
SNSなど様々な情報があふれる中での子育ては便利な反面、根拠に乏しいものや、かえって子どもの本来の成長発達を妨げるものまで潜んでいることがあります。
私たちスタッフは各分野の学会や研修会に積極的に参加し研修を重ね、日々学び続けています。
法人グループ内(みくりキッズくりにっく・コドモノいっぽクリニック・やおやコドモくりにっく・まんまる・七つの海・KNOT)のカンファレンスも定期的におこない、互いに情報の共有につとめています。
最新の知見と信頼ある情報を常にアップデートし、根拠に基づいた質の高い診療をグループ全体でおこなっています。
これからの時代は医療のDX化も必要です。
ネット予約、電子カルテ、WEB問診など患者様の大切な診療情報を適切に管理し、診療サービスの向上を図ります。
施設コンセプト
あのねコドモくりにっくは一般社団法人みくりエイティブがデザインを担当しました。
子どもたちの「あのね」に向き合うクリニック
環状八号線沿いの南向きの大きな窓からは陽がたくさん差し込みます。
その光は天気や時間によって変化します。
子どもたちが伝えたい想い「あのね」も刻々と変化します。
たのしかったこと、うれしかったこと、こわかったこと、寂しい気持ちに不安な気持ち・・
子どもたちの日々変化する「あのね」を色とりどりに表現しました。

みくりキッズくりにっく、コドモノいっぽクリニック、やおやコドモくりにっく、そしてあのねコドモくりにっく4つのクリニックに共通するデザインがトイレの【3つの蛇口】と受付下の【ネズミの穴】です。
世の中がとても便利になり、手をかざすだけで適温の水で手を洗うことができる水洗が増えました。
ちょっとした日常動作の中の子どもたちの手先の細かな動きを大切にしたいと考え、トイレの水洗を大人用とこども用に分け、こども用水洗には3つの種類の違う蛇口をつけました。
押したり、ひねったり、どうやったら水が出るのか・・見たこともない蛇口への挑戦です!

ねずみの穴?なかには何かがいるのかな?
ドキドキしながら、勇気をだして手をそーっといれてみる・・
そんな子どもたちのちょっとした「はじめてチャレンジ体験」を見守りながらあとおしできるといいな。の想いをこめて不思議な穴を作りました。